
どっちがいい?

続けるか悩んでます…
大人気の商品となっています。
アメリカに投資するべき理由を
まとめています。
◆ オルカンとS&P500の違い
◆ 私が米国に投資する根拠3選
ぜひ見てください!
キーワードは
『ほったらかし投資』です。
銘柄スカウターがオススメ
利用料は無料なので
何も気にせず使えるが素晴らしいです。
\こちらをクリック/

改めましてこんにちは!
たいか(Twitter:Taica)です。
31歳で資産2000万円を突破
さらにFIREに向けて
節約・投資を学んでます。
![]()
にほんブログ村
応援クリックいただけると嬉しいです🔥
証券口座を開くならSBI証券がオススメ
手数料も業界最安値でポイント投資も充実
\高配当株選びするならクリック/
\自己紹介の詳細はこちら/
2000万円投資した結果はこちらです。


結果だけ知りたい方は
最後のまとめにどうぞ☺
目次に戻る
こちらのオススメ記事も
お役に立てると思うのでぜひ見てほしいです👇
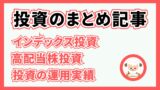
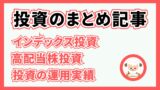
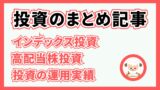
オルカン vs S&P500どちらに投資する?
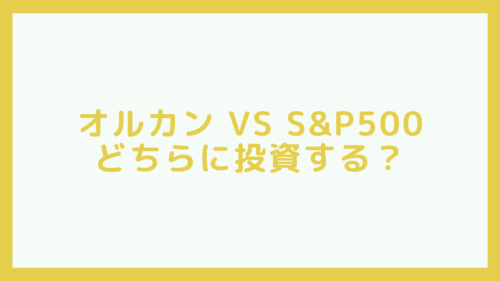
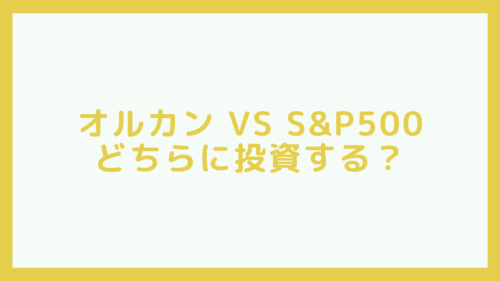
どちらがいいのか?
永遠の課題ですよね?
どちらかに投資していること
投資していることが大切。
いかにミスをしないかが大切💡
やめてしまうのが一番のNGです。
次のことが気になりますよね?


オルカンとS&P500
どっちがいいの?
確かにそうですよね💡
ちなみに私はS&P500派です。
その理由は後半に説明しますね。
改めて違いを整理しましょう
オルカンも6割は米国に投資されてます💡
日本も5~6%、中国に3~4%に投資されてます。
構成銘柄のトップ10はこちら
オルカンとS&P500の構成銘柄ランキング10
| 上位10銘柄 | オルカン | S&P500 |
|---|---|---|
| アップル | 3.6% | 5.8% |
| マイクロソフト | 2.9% | 5.4% |
| アマゾン | 1.3% | 2.2% |
| バークシャー・ハサウェイ | 0.7% | 1.7% |
| アルファベット(CL-A) | 0.9% | 1.6% |
| ユナイテッドヘルス | 0.8% | 1.4% |
| アルファベット(CL-C) | 0.8% | 1.4% |
| ジョンソン&ジョンソン | 0.8% | 1.4% |
| エクソンモービル | 0.8% | 1.3% |
| JPモルガン・チェース | 0.7% | 1.2% |
| トップ10の合計 | 13.3% | 20.4 |


って上位は全部一緒なんだ!!!
オルカンは上位銘柄の比率が下がって
分散される企業数が多いのが特徴
ってデータからも見てもわかりますね💡
だからこそ
オルカンでもS&P500でも
どちらでも投資していることが大事!!
投資信託の販売金額ランキング
ちなみにSBI証券の
投資信託のランキングはこちらです。
第2位:eMAXIS Slimオール・カントリー
第3位:eMAXIS Slim S&P500
オルカンとS&P500の比較
| オルカン | SBI-V-S&P500 | eMAXIS Slim S&P500 | |
|---|---|---|---|
| 管理手数料 | 年0.05775% | 年0.0938% | 年0.0968% |
| 純資産総額 | 1.36兆円 | 1.06兆円 | 2.50兆円 |
| 連動指数 | MSCI-ACWI | S&P500 | S&P500 |
10万円投資しても200円以下💡


これだけ言っているのに
なんでS&P500派なの?
理由は一つで
アメリカへの投資の方がリターン高い
って考えているからです。


具体的にどういうことか
これから説明しますね💡
オルカンより米国(S&P500)をオススメする理由3選
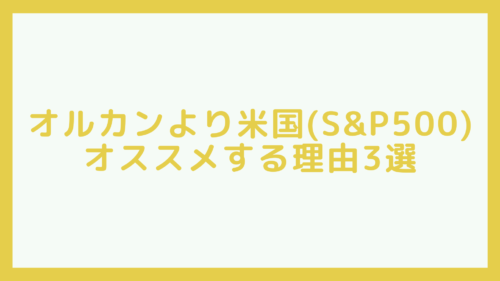
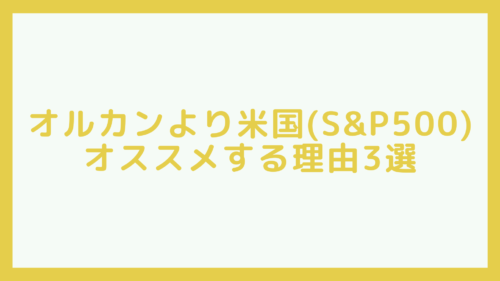
オルカンのメリットは
アメリカより他国が覇権国になったら
その国の恩恵を受けられるからです。
でも、
そんな国が現れなければ、
アメリカだけに投資した方がいいですよね。


S&P500とVWOのチャート


念のため私も1株投資してます。
でも悲しいリターン💦
いきなり爆発する可能性はゼロではないです。
アメリカに充分期待する価値ありです。
理由3つはこちらの通り
2. 2100年まで人口が増え続けるから
3. 株主を大切にする文化があるから
オルカンも非常に優れたファンドです。
そちら目線の記事もまとめたのでぜひ
1. GDPが世界一位だから
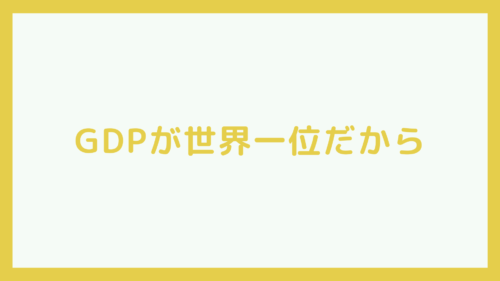
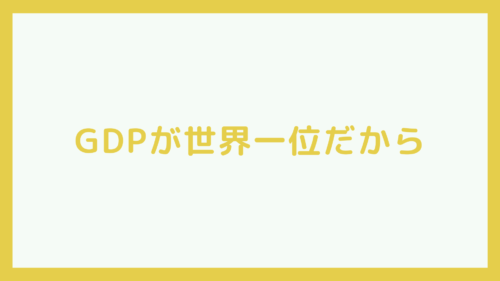
グラフを見れば一目瞭然ですね💡
アメリカの圧倒的な1位
中国もグングン差し迫っている状態で2位
それ以降はケタが下がって
我らが日本が第3位


すみません…
いまさらですが
GDPが高い方がいいの?
GDPとは「Gross Domestic Product」の略
「国内総生産」のことを指します。
国内で産出された付加価値の総額で、
シンプルに伝えると付加価値とは利益のこと。
つまり
どれだけの利益を生み出されたか知ると
国の経済状況を端的に知ることができます。
だからこそ
世界第1位のアメリカの経済は明るいです💡
過去のアメリカのGDP推移
過去のアメリカのGDP推移も見よう!


メッチャキレイな
右肩上がり!!!
唯一、2009年と2020年がマイナス成長…
リーマンショックとコロナショックですね。
それ以外はプラス成長ってのが
スゴク安心感がありますね💡
5年CAGR:4.2%
10年CAGR:4.4%
20年CAGR:4.2%
素晴らしいですね!!
(N年の数値÷初年度の数値)^(1/N-1) – 1
難しいのでふーんって感じでOK
中国・インドのGDPの推移
こんな疑問がわきませんか?


投資で大事なのは
「過去」より「未来」
中国とかインドは抜かさないの?
中国の伸びはとんでもないですね
5年CAGR:9.6%
10年CAGR:10.1%
20年CAGR:14.6%
アメリカ超えて1位になるのでは?
ってことは中国に投資する
もしくは米国だけでなく
中国含むオルカンがいいんじゃない?
中国もいいやん!って感じますよね💡
日本のGDP推移
日本の名目GDPの推移も確認しました。


ふぁ!???
結構ショック…
気持ちはこんな感じですね💦
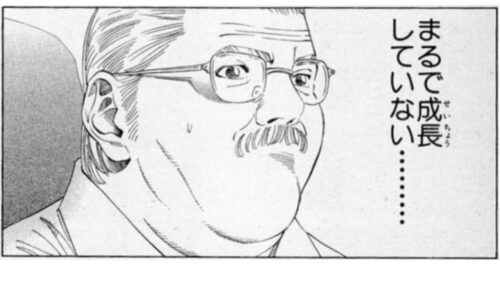
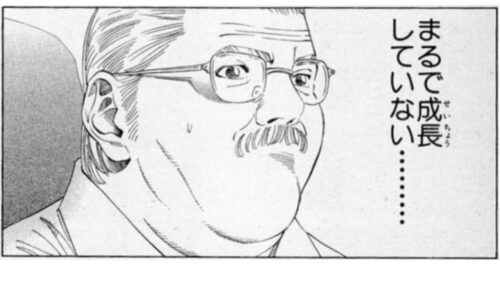
引用:スラムダンク 22巻 井上雄彦
話しはそれちゃいましたが、
結論
アメリカを投資する理由の1つ目は
『GDPが世界一位だから』
です!!
米国以外の国ではどういう動きなのか
ヨーロッパやカナダなどの先進国から
中国・インド・南アメリカやアフリカと新興国まで
徹底分析しているのでこちらもみてください☺
2. 2100年まで人口が増え続けるから
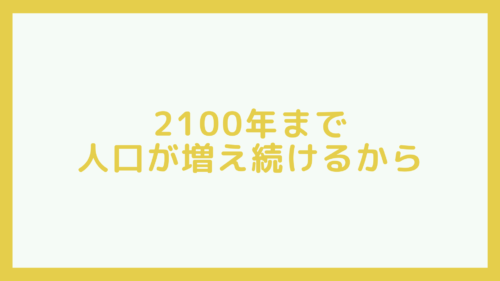
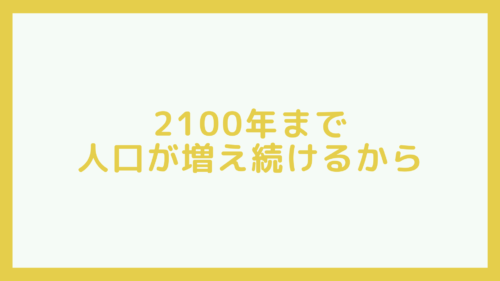
未来のGDPを推測するには
人口推移を確認するのがいいです💡
・純粋な需要拡大
・企業の積極的な投資
・新たな市場が芽生え拡大
これらのメリットの結果
経済成長してGDPも上昇しますね💡
そして人口推移は
明日明後日にいきなり予想が変わる
なんて劇的なことは起こらないです。
いきなり子供がたくさん生まれないですよね。
いきなり大量の移民は来ないですよね。
だからこそ
未来を推測しやすい指標の一つです。
世界人口としては2100年まで増加見込み
2023年は80.5億人
2100年は103.5億人
⇓
GDP上がる
⇓
企業株価も上がる
この流れですね💡
米国・中国・インド・新興国の人口推移を比較
ここで
各国の人口推移を見てみよう!!
| 国名 | 2023年の人口 | 2100年の人口 | 人口ピークの年 | 人口ピークの数 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 3.4億人 | 3.9億人 | 現在進行中 | 現在進行中 |
| 中国 | 14.3億人 | 7.7億人 | 2021年 | 14.3億人 |
| インド | 14.3億人 | 15.3億人 | 2066年 | 16.9億人 |
| 日本 | 1.2億人 | 0.7億人 | 2009年 | 1.3億人 |
| ブラジル | 2.2億人 | 1.8億人 | 2047年 | 2.3億人 |
| ナイジェリア | 2.2億人 | 5.5億人 | 現在進行中 | 現在進行中 |
・中国、インドも2100年までに人口減少
・アメリカは2100年まで常に人口増加
・アフリカ諸国は人口増加
わかりやすいですね。
一つは出生率が2.0以上
もう一つは他国から移民
アメリカの出生率は2.0以下であり
移民による人口増加の影響が大きいです。
アメリカで産まれれば自動的に米国籍です。
移民したい人が来ると言われます。


GDPって
労働人口が多い方がいいのでは?
確かに人口多くても
少子高齢化だと大きな需要がないです。
人口ピラミッドも確認💡
米国・中国・インドの労働人口の比較
高齢人口が少なく、労働人口が多いです。
需要も多く、将来期待値も大きいですよね。
アメリカの力強さを無視できないですね🔥
アメリカを投資する理由の2つ目は
です!!
3. 株主を大切にする文化がある
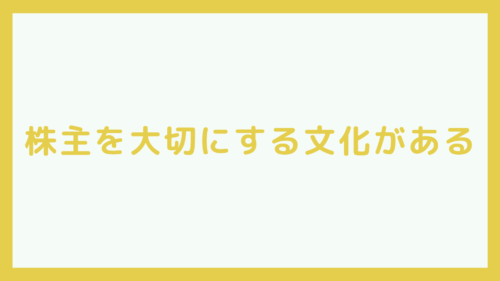
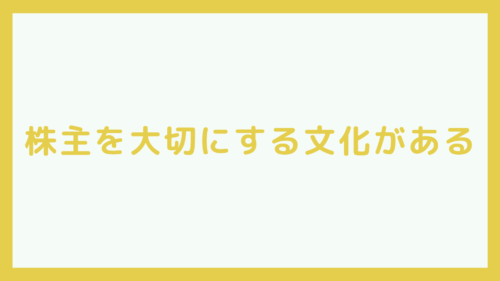
日本は従業員重視の傾向あり
日本とアメリカは大きな違いがあります。
※最近はアメリカも考え方が広がって
ステークホルダー主義と変わってきてます。
投資家、直接顧客、一般消費者、従業員、金融機関、政府、地域社会、従業員家族など
とはいえ
ステークホルダーの中に株主もいます💡
ということで
アメリカは他国に比べて株主重視であり
投資家にとって法整備も整っています。


アメリカは株主重視なんですね。
実際、企業データありますか?
定量的なデータとしては
連続増配年数を見てみましょう!!
日本だと売上利益が下がると
すぐに配当金が減配してがっかり…
これって考え方によっては株主側に
利益減少の費用を押し付けてますよね。
でもアメリカ企業の考え方は
売上利益の減少は経営者の責任
株主への還元を大切にしているので
配当金を減配にしない企業も多いです。
改めて
連続増配当のトップ企業をまとめました💡
馴染み深い企業をピックアップしてます。
アメリカ企業の連続増配年数のランキング
マネックス証券の銘柄スカウターで調べられます。
URL:https://info.monex.co.jp/market-information/tool/us-expectation.html
| 企 業 名 | 取 り 扱 い 商 品 | 連 続 増 配 当 年 数 | 増 配 当 ラ ン キ ン グ |
|---|---|---|---|
| P&G | パンパース アリエール ファブリーズ | 65年 | アメリカ 第3位 |
| 3M | ポストイット バイオ医薬品 スマホ部材 | 63年 | アメリカ 第8位 |
| J&J | アキュビュー バンドエイド リステイン | 59年 | アメリカ 第10位 |
| コカ・コーラ | コカ・コーラ いろはす 綾鷹 | 59年 | アメリカ 第10位 |
| 花王 | メリーズ キュキュット めぐりズム | 34年 | 日本 第1位 |


!!!!!!!
こんな連続増配しているの!!??
このデータ見た時は衝撃じゃないですか?
60年以上もの連続増配当って
メチャクチャ安心感ありますね。
いつも利益も増加しているないですよ。
具体例:P&Gの株価
・ ブラックマンデー
・ ITバブル崩壊
・ リーマンショック
・ チャイナショック
・ コロナショック
増配を継続するのは株主重視ですよね🔥
20社、30社とあるのは素晴らしいですよね!
日本企業の連続増配はどのくらい?
日本だと20年継続企業は20社です。
20年継続:19社
未来も絶対とは言えません。
株主重視マインドには変わらないですね💡
株価や配当金が上がりやすことを意味してます。
まとめ
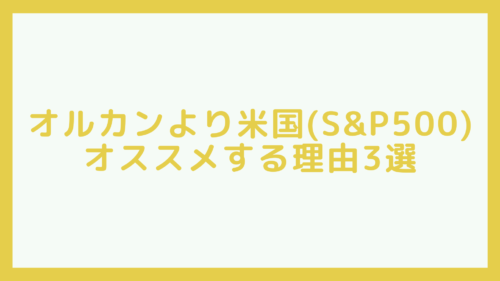
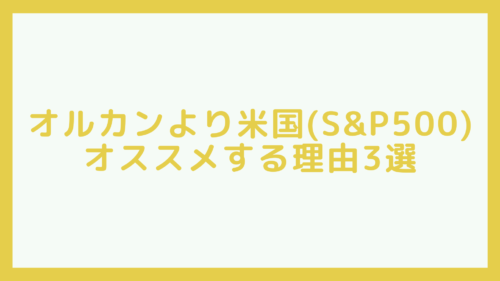
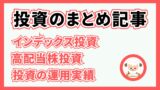
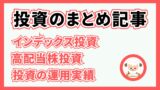
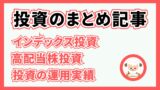
ありがとうございます!
オルカンとS&P500を知っておきたいですよね。
読んでいただけるとお役に立つと思います。
『eMAXISシリーズの落とし穴』
オルカン vs S&P500
どちらか投資している時点でOK
私はS&P500(米国)派です。
2. 2100年まで人口が増え続けるから
3. 株主を大切にする文化があるから
GDPの動きと人口動向は
1年に1回は確認した方がいいです。
GDPのシナリオも変わります。
1年に1回程度でいいので
普段はドン!っと落ち着きましょう。
皆さんの投資方針のお役に立てたら嬉しいです。


最後まで読んでいただき
ありがとうございました!!
![]()
![]()
にほんブログ村
応援クリックいただけると励みになります🔥
こちらも読むと人生楽しむヒントになります💡


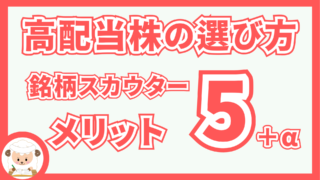
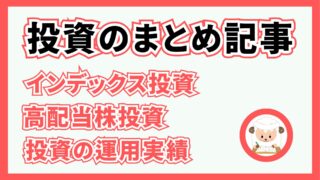
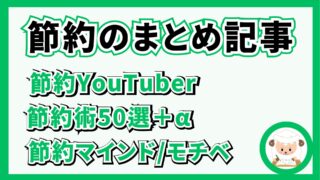


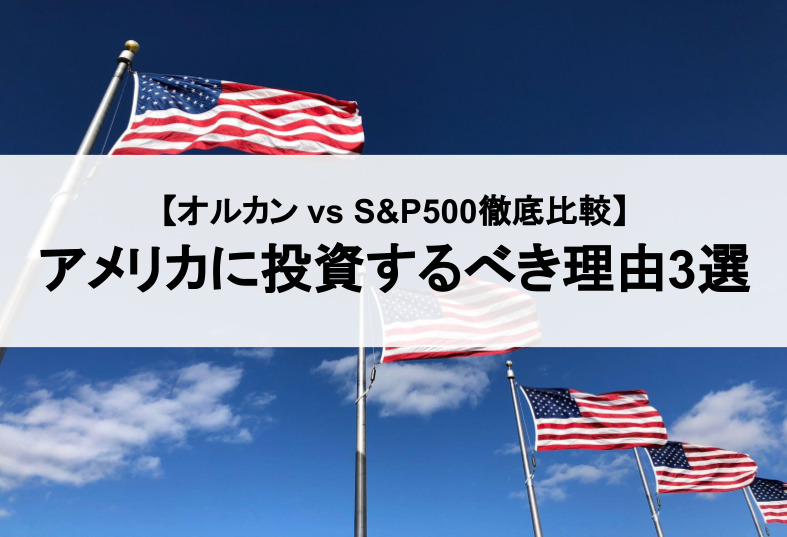

![SBI証券[旧イー・トレード証券]](http://taica-1growth-perday.com/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif)
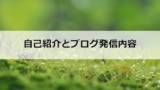


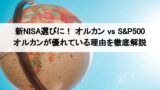

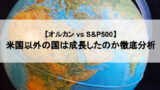
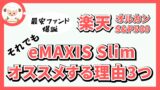

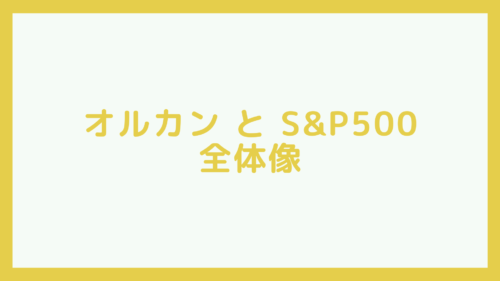
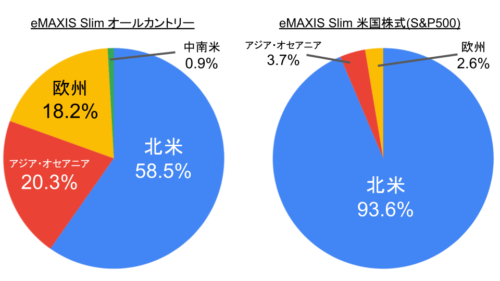

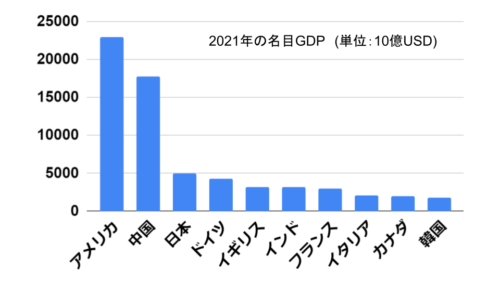
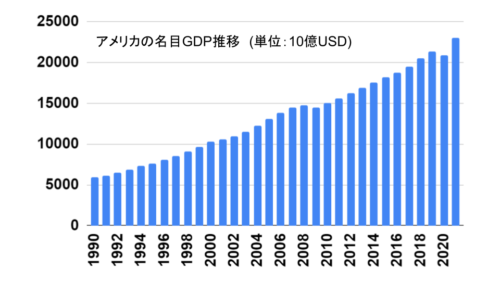


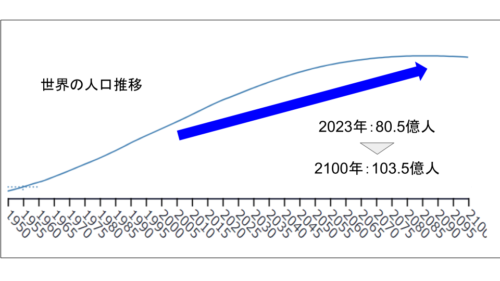
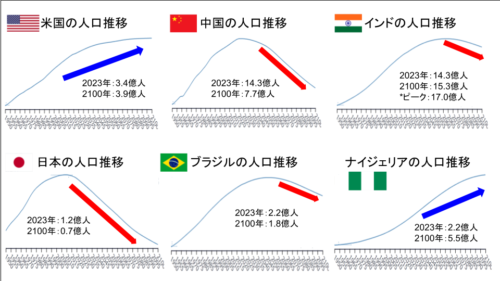
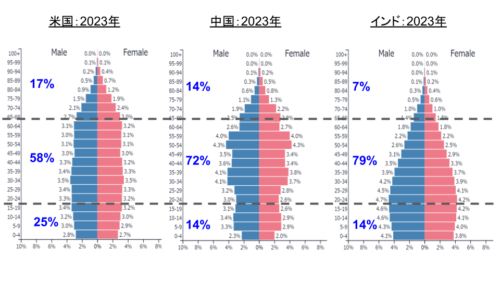
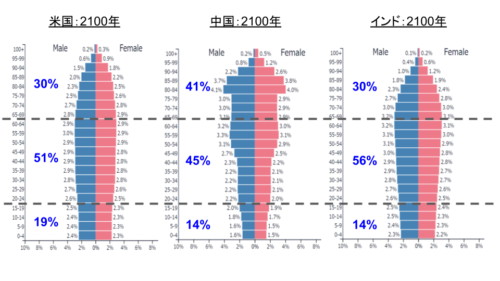

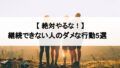
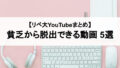
コメント